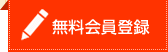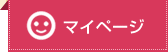転職・求人情報-名古屋市、愛知県、岐阜県、三重県の転職・求人サイト
- 中日しごと情報HOME>
- 就職・転職ニュース>
- 【暮らし】<うぇるかむシニア>自立促す仕事づくり 古書販売で障害者の就労を支援 近藤 豊彦さん68歳
【暮らし】<うぇるかむシニア>自立促す仕事づくり 古書販売で障害者の就労を支援 近藤 豊彦さん68歳
2010/01/20
薄いハトロン紙に包まれた本が、ずらりと書棚に並んでいる。「これは、なかなかいい本ですよ」。近藤豊彦さんは一冊を手に取り、いとおしそうに眺めた。
名古屋市のNPO法人「マイライフ・ステーション協会」。またの名を「小説館 以心堂」。近藤さんは、自分が収集した本や寄付された本の販売を通して、障害者の就労を支援している。
若いころから、小説の初版本を集めるのが趣味。銀行員時代は、出張先で古書店に立ち寄り、購入した本を宅配便で自宅に送った。「読むのも好きですが、とにかく集めるのが好き」。近藤さんが買った高価な本を読んでいた妻に「読んだら駄目」と言ったら、「本は読むものではないのですか」と切り返されたことも。「家が一軒建つほど」のお金をかけて集めた本は、二万冊近くになる。
四十八歳の時、網膜剥離(はくり)で左目を失明。右目にも症状が出て「仕事に戻れなかったら古書店をやろう」と古物商の免許を取った。幸い職場に復帰でき、定年まで勤め上げた。
退職した翌年の二〇〇一年、親せきに「図書館の館長にならないか」と誘われ、社会福祉法人「名古屋ライトハウス」の名古屋盲人情報文化センター所長に。「図書館長なんてかっこいいと思って。点字図書館でしたが」
視覚障害者の福祉にかかわるうち、障害者全体の就労問題を考えるように。災害備蓄用のパン缶詰製造など、工賃アップに取り組んだ。〇六年、障害者の自立を支援する同協会を設立した。
多くのアイデアの中の一つが古書販売。寄付された古書を授産施設などできれいにして売る。ライトハウスの理事を退職した昨年三月から、本格的に取り組み始めた。
活動を知った人から早速「古本の量販店に持って行っても安いし、人の役に立つなら」と本が寄せられた。市内の授産施設で働く人が整理。即売会などで売り、施設の収入につなげている。
三省堂が昨年十月、東京に開いた古書専門店「三省堂古書館」には、以心堂として出店。近藤さんの貴重な初版本を置いている。高い元手がかかっているため、利益の半分は近藤さんが受け取り、残りは整理の作業をしている障害者の工賃などに。古書のデータ入力がもう少し進んだら、インターネット販売も始める。
「朝市やハウスクリーニングなど、工賃アップを図るアイデアはほかにもたくさんあります」と近藤さん。障害者の自立支援の取り組みは、まだまだ広がりそうだ。 (境田未緒)
◆若い世代へ 社会との接点持って
家族の生活もあるので、仕事にベストは尽くさなくてはいけないが、会社が人生のすべてではない。これからの時代は、若いうちから社会とのつながりを持ち、社会の中で力を持つことが大切になる。地元の子どもたちに野球を教えることでも、趣味の仲間をつくることでも、何でもいい。違う世界の人と付き合い、その考えを知ることで自分の世界が広がり、ひいては仕事にも役立つ。社外の付き合いを増やし、たくましく、しなやかに生きてほしい。
転職・求人情報検索(名古屋市・愛知県・岐阜県・三重県)はトップから
- 2025/09/11
- 【愛知】ひきこもりや高齢者ら 前向けるよう
- 2025/09/09
- 【愛知】突発的に看護師が足りない!どうする?
- 2025/08/29
- 【社会】夫婦の働き方 十組十色 広がる「ファミリーキャリア」
- 2025/08/27
- 【くらし】地方回帰 移住は今/転職で「生活の質 向上」異動打診機に決意
- 2025/08/22
- 【経済】県内最低賃金1140円に63円引き上げ、審議会答申
- 2025/08/14
- 【社会】保育施設8割 人材不足 政府が初の全国調査
- 2025/08/13
- 【社会】働きながら介護や育児 10年後には・・・ 6人に1人
- 2025/07/18
- 【三重】ビジネスプラン作り 基本から 「グランプリ」向け 相可高生学ぶ
- 2025/07/08
- 【地域経済】子育て・介護しやすく 「短時間正社員制度」を導入
- 2025/06/20
- 【愛知】終業と始業の間 しっかり休息を