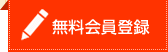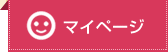転職・求人情報-名古屋市、愛知県、岐阜県、三重県の転職・求人サイト
- 中日しごと情報HOME>
- 就職・転職ニュース>
- やってみました 記者たちの職業体験ルポ 森林普及指導員
やってみました 記者たちの職業体験ルポ 森林普及指導員
2009/10/28
林業思い地道な調査
市域の約七割を森林が占める豊田市は、山の整備に力を入れている。森に関する取材も多いが、訪れるのは間伐体験用の市有林や整備された県有林などがほとんど。実際の森の状況はどうなのか-。県豊田加茂農林水産事務所の森林普及指導員の調査に同行した。
市、森林組合、山主の「森づくり会議」で手入れをする山「森づくり団地」を決める。指導員は団地を調査し、山主にどう整備していくかなどの情報を提供。同事務所独自の取り組みで今回は同市御所貝津町の十七ヘクタールの団地を調査した。
同事務所の村田典之主査(38)ら四人と山に入った。衛星利用測位システム(GPS)と地図を片手にスギやヒノキの生い茂る私有林を進む。整備された道は無く、地面はぬかるみ、しばしば足をとられる。
調査地はスキー場でも、めったにお目にかかれない急斜面。記者は足を滑らせ十メートルほど滑落した。けがは無かったが、危険な調査だと実感した。
調査地に着くと、直径一・五センチ、高さ二メートルの紅白ポールが活躍する。木の前に立て、太さを推測し、生育状況を見て写真に収める。「ポールを立ててきて」との指示が出る。簡単な作業だが、足元の倒木や落ち葉に邪魔され数メートル進むのも大変。ポールを立てた時は汗びっしょりだった。
団地の名の通り、一つの山に複数の山主がいる。境界を探るため、県が山主の申告で山の状況をまとめた「森林簿」を手に、植えてある木の種類、樹齢などに気を配り歩く。境界だと判断した場合にポールを立て写真を撮影する。自分の所有地が分からない山主もいるので、所有地を確定させるのに役立てることも調査の目的の一つだ。
一日かけ隅々まで調査。一週間後に山主に報告する。今回は一日で終わったが、真夏に三日間調査を続けることもある。秋には間伐が始まるためだ。大変な調査への意欲はどこからくるのか。「林業を再生したい。山主さんに正確な情報を提供して手入れを始めてもらうことから始まる。小さなことの積み重ねが大切」と村田さん。地道で根気がいる作業への情熱に頭が下がる思いがした。(渡辺陽太郎)
【メモ】森林普及指導員は国家試験を受け資格を取らなくてはならない。受験資格は高卒以上で、林業関係での実務経験が4年以上必要。資格を取り県職員として採用され、辞令が出て初めて仕事に就ける。初任給は16、17万円ほどで上限2万5000円の指導員手当がつく。

- 土地の境界を探る村田さん。GPSで現在地を確かめ正確に記録している=豊田市御所貝津町の私有林で
転職・求人情報検索(名古屋市・愛知県・岐阜県・三重県)はトップから
- 2025/09/11
- 【愛知】ひきこもりや高齢者ら 前向けるよう
- 2025/09/09
- 【愛知】突発的に看護師が足りない!どうする?
- 2025/08/29
- 【社会】夫婦の働き方 十組十色 広がる「ファミリーキャリア」
- 2025/08/27
- 【くらし】地方回帰 移住は今/転職で「生活の質 向上」異動打診機に決意
- 2025/08/22
- 【経済】県内最低賃金1140円に63円引き上げ、審議会答申
- 2025/08/14
- 【社会】保育施設8割 人材不足 政府が初の全国調査
- 2025/08/13
- 【社会】働きながら介護や育児 10年後には・・・ 6人に1人
- 2025/07/18
- 【三重】ビジネスプラン作り 基本から 「グランプリ」向け 相可高生学ぶ
- 2025/07/08
- 【地域経済】子育て・介護しやすく 「短時間正社員制度」を導入
- 2025/06/20
- 【愛知】終業と始業の間 しっかり休息を