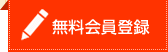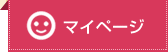転職・求人情報-名古屋市、愛知県、岐阜県、三重県の転職・求人サイト
- 中日しごと情報HOME>
- 就職・転職ニュース>
- 【健康】職場のうつ病(4)メンタルヘルス対策 環境改善と会話が重要
【健康】職場のうつ病(4)メンタルヘルス対策 環境改善と会話が重要
2009/07/24
職場では、従業員の心の健康(メンタルヘルス)維持向上が大切だ。それを損ねずに、いかに快適に働き続けられるか。企業の取り組みが、ますます重要になっている。 (鈴木久美子)
ふだんと様子が違う部下がいたら、管理職はどう部下の話を聞くのか。それを実践するための「積極的傾聴法」を学ぶセミナーが七月中旬、東京都港区で開かれた。会場には全国から管理職や企業内の保健師ら産業保健スタッフ約四十人が集まった。
二人一組で話し役と聞き役に分かれ互いの話を聞く。うつ病で休職・復職したが本調子でない部下の悩みを聞く練習も体験。「相手が本当に気にしている中核の話にどう持っていけばいいのか」「問題を周りのせいにする部下への対応に悩んでいる」と参加者から切実な声が上がる。
参加企業の人事部チームリーダー(54)は「いかに心の不調者を出さないかが課題。会社に持ち帰って管理職向けに研修したい」と話した。
企業のメンタルヘルス対策は、二〇〇〇年に厚生労働省が指針を示した。同年、自殺した大手企業従業員の遺族が起こした民事訴訟の最高裁判決で、初めて長時間労働とうつ病、自殺の因果関係が認められてもいる。このころ取り組み始めた企業が多い。
指針では、本人・管理監督者・産業保健スタッフ・外部の専門家のそれぞれのケアの継続が必要とした。具体的には、従業員への相談窓口を設けたり、管理職らに研修を行うなどだ。
「本人や周囲に異変の『気づき』があったらすぐ相談・対応するよう教育」(JFEスチール)、「社員がストレスの具合を自分で確かめるチェックリストを用意」(三菱化学)、「相談窓口を複数設けている」(ホンダ)、「復職判断時に家族も面談」(イーグル工業)、「若手の寮で寮母にみていてもらう」(JR東日本)などもある。
企業と契約し従業員の相談や職場改善の提言などを行う「EAP(従業員支援プログラム)」専門企業も、一九九〇年代後半から増えてきた。その一社、「イープ」の西川あゆみ社長は「こちらに『お任せ』ではなく企業側もまじめに取り組むと、不調者の早期発見だけでなく、不調者を出さない予防になる」と企業トップや人事担当者の意識が対策を進めるカギと話す。
従業員がセルフケアできるよう、中央労働災害防止協会がチェックリスト「職業性ストレス簡易評価」を、HP(同協会で検索)で公開するようにもなった。
だが同省の調査(〇七年)で、メンタルヘルス対策に取り組む企業は、大手では多いが中小企業ではなかなか進まず、全体では33・6%。
「職場が抱える問題を根こそぎ取り除かないと対策が追いつかない」。日本生産性本部メンタル・ヘルス研究所の楠宏太郎主任研究員は指摘する。
同研究所の昨年調査では、企業が対策に期待する目的は「不調者の早期発見」がトップ(78・4%)。心の不調者本人を問題ととらえる傾向があるが、楠研究員は「職場の環境改善こそが必要」と言う。
調査では「職場に人を育てる余裕がなくなっている」と回答した企業は八割。同時に「人を育てる余裕」「組織・職場とのつながり感」「仕事の全体像や意味を考える余裕」のいずれかに「なくなってきている」と回答した企業は、そうでない企業に比べて心の病が増えた割合が約二割高かった。
「仕事の意味を互いに認識しあってできるよう会話が重要になる。会話があれば誰かが倒れるまで気づかないということもないだろう。組織全体で取り組まないと、間に合わない」と楠研究員は話す。
=おわり
転職・求人情報検索(名古屋市・愛知県・岐阜県・三重県)はトップから
- 2025/09/11
- 【愛知】ひきこもりや高齢者ら 前向けるよう
- 2025/09/09
- 【愛知】突発的に看護師が足りない!どうする?
- 2025/08/29
- 【社会】夫婦の働き方 十組十色 広がる「ファミリーキャリア」
- 2025/08/27
- 【くらし】地方回帰 移住は今/転職で「生活の質 向上」異動打診機に決意
- 2025/08/22
- 【経済】県内最低賃金1140円に63円引き上げ、審議会答申
- 2025/08/14
- 【社会】保育施設8割 人材不足 政府が初の全国調査
- 2025/08/13
- 【社会】働きながら介護や育児 10年後には・・・ 6人に1人
- 2025/07/18
- 【三重】ビジネスプラン作り 基本から 「グランプリ」向け 相可高生学ぶ
- 2025/07/08
- 【地域経済】子育て・介護しやすく 「短時間正社員制度」を導入
- 2025/06/20
- 【愛知】終業と始業の間 しっかり休息を