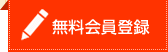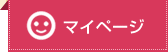転職・求人情報-名古屋市、愛知県、岐阜県、三重県の転職・求人サイト
- 中日しごと情報HOME>
- 就職・転職ニュース>
- 【三重】緊急雇用創出事業がスタート 基金活用も高いハードル
【三重】緊急雇用創出事業がスタート 基金活用も高いハードル
2009/07/06
仕事を失った人に地方自治体が6カ月の短期雇用を提供する緊急雇用創出事業が、県内でも始まっている。事業のために国の資金で県が設けた基金は105億円。県と市町は基金の活用を急ぐが、事業を進めるための課題も見えてきた。
派遣社員として、3月末まで菰野町の自動車部品工場で働いていた北爪浩之さん(47)。今は、昨年9月の豪雨で荒れ果て、観光客の足が遠のいた鈴鹿山脈の散策路の整備工事に汗を流す。菰野町が基金から1400万円を使って雇用した6人のうちの一人だ。
勤務は1日8時間で週5日。日当は1万3300円だ。3月末に「派遣切り」に遭ったときは「この年齢では仕事がない。若い人もたくさん失業してるし、どうしようか…」と落ち込んだが、「今は体を使った仕事にやりがいがある」と前向きになった。この仕事をしながら再就職先を見つけるつもりでいる。
◇
「3万人分の仕事が足りていない」。県勤労・雇用支援室の小山衛室長は危機感をあらわにする。5月のデータで、求職者数と求人数の差は3万人。県内の有効求人倍率は過去最悪の0・4を記録した。
基金を活用する事業で、5月末までに県と市町が雇用したのは368人にとどまる。これまでに実施が決まった事業を合わせても、雇えるのは2500人程度にすぎない。小山室長は「基金をすべて使えば8000人以上の仕事ができる」とみて、「県の部署や市町には『使えるだけ使ってほしい』と伝えている。基金は3年分だが、ことしですべて使い切る気持ちでいる」と話す。
一方、事業を企画する側の県や市町の担当者からは、基金の使いにくさを指摘する声もある。基金を使うには「新規事業に限る」「事業費のうち人件費が7割以上」などの要件をクリアしなければならず、実際に事業を組むまでのハードルが高いからだ。
菰野町が企画した散策路整備のように、自治体が手を付けたくても、これまで実施をためらってきた6カ月程度の仕事があればいいが、「なかなか適当な仕事が出てこない」(小山室長)のが実情だ。
菰野町の担当者は「本当に必要なサービスは、半年でやめるわけにはいかない。基金終了後に自治体が負担し続けなければならないとしたら、それは困る」と打ち明ける。
野呂昭彦知事は5月末、厚生労働省に雇用期間を延長できるよう要望した。四日市市なども東海市長会を通じて要件の緩和を要望する方針だ。
【緊急雇用創出事業】失業者に一時的なつなぎの雇用を提供するための事業で、雇用期間は原則6カ月未満。自治体による直接雇用と、自治体が委託した民間団体による雇用がある。
事業費は国からの緊急雇用創出事業臨時特例基金の105億7000万円でまかなう。
国の長期的な雇用対策には、「ふるさと雇用再生特別交付金」の事業や職業訓練などもある。
<視線>緊急雇用創出事業を紹介しているハローワークや自治体の担当者から、「応募は中高齢者がほとんど。若い人が少ない」「製造業の失業者に紹介できる事業がない」との声を聞いた。幅広い年代や業種に解雇が広がっている中、迅速性に加え多様な事業を提供することが急務だ。
雇用できれば何でも良いとも思わない。観光や一次産業の振興、福祉サービスの充実など、失業者の救済と同時に、地域の将来につながる事業の企画にも期待したい。

- 豪雨で荒れた散策路の倒木や石を片づける就業者たち=菰野町千草で
転職・求人情報検索(名古屋市・愛知県・岐阜県・三重県)はトップから
- 2025/09/11
- 【愛知】ひきこもりや高齢者ら 前向けるよう
- 2025/09/09
- 【愛知】突発的に看護師が足りない!どうする?
- 2025/08/29
- 【社会】夫婦の働き方 十組十色 広がる「ファミリーキャリア」
- 2025/08/27
- 【くらし】地方回帰 移住は今/転職で「生活の質 向上」異動打診機に決意
- 2025/08/22
- 【経済】県内最低賃金1140円に63円引き上げ、審議会答申
- 2025/08/14
- 【社会】保育施設8割 人材不足 政府が初の全国調査
- 2025/08/13
- 【社会】働きながら介護や育児 10年後には・・・ 6人に1人
- 2025/07/18
- 【三重】ビジネスプラン作り 基本から 「グランプリ」向け 相可高生学ぶ
- 2025/07/08
- 【地域経済】子育て・介護しやすく 「短時間正社員制度」を導入
- 2025/06/20
- 【愛知】終業と始業の間 しっかり休息を