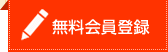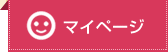転職・求人情報-名古屋市、愛知県、岐阜県、三重県の転職・求人サイト
- 中日しごと情報HOME>
- 就職・転職ニュース>
- やってみました 記者たちの職業体験ルポ 養蚕農家
やってみました 記者たちの職業体験ルポ 養蚕農家
2009/06/25
伝統支える強い思い
戦前は日本経済のけん引役とも言われた養蚕業。記者も四十年近く前、理科の授業で蚕が繭を作る様子を観察した記憶がある。化学繊維の普及で黄金期は遠い過去になり、養蚕農家は絶滅寸前。県内では新城市で二軒の農家がなお取り組んでいると聞き、春蚕シーズンを迎えた六月初め、同市出沢の海野久栄さん(83)方を訪ねた。
小さな体育館ほどの広さがある二棟続きの作業場。桑の葉をたっぷりと食べ、体長八センチほどに丸々と太った蚕に、海野さんは桑の葉を覆いかぶせるように与えていた。三万匹が身をくねらせるようにし、旺盛な食欲をみせている。餌やりは簡単だったが、蚕の数には圧倒される。映画の「モスラ」が夢に出てきそうだ。
片隅には製糸機械や乾燥機、はかりなどがずらり。資料として保存してあるだけで使っていない道具も。「今は製糸は群馬県の業者に依頼している。蚕を育て、繭を作るまでが仕事」という。
繭を作る工程は実に合理的だった。蚕は糸を吐き出す準備が整うと餌を一切食べなくなる。ころ合いを見計らって、蚕が繭を作る木枠「回転簇(かいてんぞく)」を蚕の群れの上に並べておくと、高い所に上がる習性がある蚕たちは次々とはい上がって来る。
回転簇には、段ボール紙を組み合わせ碁盤の目のようにした、一匹がちょうど収まる数センチ四方の「蚕の家」が百個以上ある。重さが偏ると、回転する仕組みだ。天井から鉄線でつり下げておけば、上へ上へと向かう蚕の重みで上下が逆転。いつの間にか巣全体でまんべんなく繭作りを始めている、というわけだ。
海野さんと一緒に、回転簇を据え付ける作業に挑戦した。いくつかの蚕はすでに糸を吐き、繭を作り始めている神秘的な様子が目の当たりにできた。幼虫が繭を作るようになるのに三週間。さなぎになるまでさらに一週間待ち、出荷する。
昭和四十年代は従業員を雇い、年七回も出荷した海野さんも今は兼業。「田植えと重なるこの時期は多忙。養蚕は割に合わない」と言うが、伊勢神宮に奉納する絹糸を作るための繭生産も、海野さんに任されている。続けるのは「伝統を残さなければ」という強い思いがあるから。七月初旬、今年も伊勢に向かう。(阿部雅之)
【メモ】かつて県内にも20万戸近い養蚕農家があったが、今や数戸に激減。海野さんは繭1キロを2000円で販売し、60キロ作るので12万円の売り上げ。最盛期の昭和40年代には年1・5トンを作った。始めるには各種の道具が必要。「勉強したいなら受け入れてもいいですよ」と海野さん。

- 蚕がまんべんなく繭を作るように、偏ると重みで回転するようになっている装置を据え付ける海野久栄さん=新城市出沢で
転職・求人情報検索(名古屋市・愛知県・岐阜県・三重県)はトップから
- 2025/09/11
- 【愛知】ひきこもりや高齢者ら 前向けるよう
- 2025/09/09
- 【愛知】突発的に看護師が足りない!どうする?
- 2025/08/29
- 【社会】夫婦の働き方 十組十色 広がる「ファミリーキャリア」
- 2025/08/27
- 【くらし】地方回帰 移住は今/転職で「生活の質 向上」異動打診機に決意
- 2025/08/22
- 【経済】県内最低賃金1140円に63円引き上げ、審議会答申
- 2025/08/14
- 【社会】保育施設8割 人材不足 政府が初の全国調査
- 2025/08/13
- 【社会】働きながら介護や育児 10年後には・・・ 6人に1人
- 2025/07/18
- 【三重】ビジネスプラン作り 基本から 「グランプリ」向け 相可高生学ぶ
- 2025/07/08
- 【地域経済】子育て・介護しやすく 「短時間正社員制度」を導入
- 2025/06/20
- 【愛知】終業と始業の間 しっかり休息を