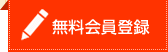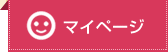転職・求人情報-名古屋市、愛知県、岐阜県、三重県の転職・求人サイト
- 中日しごと情報HOME>
- 就職・転職ニュース>
- 【社会】男性育休 日本一 福井県庁 取得2%未満→60%超
【社会】男性育休 日本一 福井県庁 取得2%未満→60%超
2025/03/13
次は「3カ月以上」目標 昨年末 平均66.4日
福井県職員の間で2%に満たなかった男性の育児休業取得率が、ここ5年ほどで60%超にまで急上昇し、都道府県別で全国トップに躍り出た。職場の環境改善はトップの意向が強く働いたといい、「育休は女性が取るもの」というかつての庁舎内の意識が大きく変わってきた。(金崎千花)
◇ ◇ ◇
カレーや鍋に、作り置きのおかず-。「それまで家の料理は週末担当でしたが、育休の間に腕が上がりました」。産業労働部の小林慶(けい)さん(29)は、東京の民間企業から転職した翌年の2023年に妻が妊娠。上司に報告すると、育休取得を勧められた。職場で「男性育休」を耳にする機会は多く、「男性も取得する自然な流れが定着していた」と振り返る。
第1子誕生後、計2カ月ほどの育休中、毎日台所に立って腕をふるった。「『父』でなければできないことは限られている」というのが最初の実感だったが、それでも「カバーできることはないか」と考え、積極的に入浴、寝かしつけなどに取り組んだ。
育児を通じて新たな仲間もできた。男性視点での情報共有や助言を受け、宅配による食材調達や、子育て支援施設の利用を妻に提案。自身の職場復帰後の、妻の負担軽減にも役立った。
育休が当たり前でない環境では「男性間で育児への共感が得られず『育児は母の担当』といった考え方が多数派のままだったかも」。自身も取得したことで、家庭での役割と仕事の両立を見直すきっかけになったといい「県庁でモデルケースができれば民間企業でも環境が整い、女性の働く選択肢がいっそう広がる可能性がある」と期待する。
総務省の23年度の調査では、都道府県庁の男性職員の育休取得率は福井が66・2%とトップ。鳥取県が64・9%、秋田県が62・8%と続く。
県人事課によると、意識醸成が進んだのは、19年に就任した杉本達治知事の号令がきっかけ。年頭あいさつや講演でも、必ず男性の育休推進を話題にする。担当者は「男性の育休推進を女性活躍に向けた一つの売りと捉え、全国から選ばれる県にしたいとの思いがあったのだろう」と話す。
庁内では、子どもを授かる男性職員が「育児参加プラン」を作成して所属長と共有し、外部の「男性育休支援アドバイザー」のカウンセリングを受ける仕組みも。人員補充などでも配慮し「取得しても大丈夫」という環境ができた。
次の段階に掲げるのが、男性職員による3カ月以上の長期取得の推進だ。ただ休むだけで育児や家事を分担しない「取るだけ育休」に終わらせず、父母対等の育児環境の実現を目指す。平均取得日数は20年度の47・3日から、24年12月末時点で66・4日に増えた。3カ月以上の取得は4割程度に伸びてきたといい、今後も工夫を重ねる方針だ。
転職・求人情報検索(名古屋市・愛知県・岐阜県・三重県)はトップから
- 2026/01/16
- 【三重】介護人材確保へアイデア発表 伊賀白鳳高生 市長や事業所職員らに
- 2025/12/23
- 【三重】追う/職場環境の整備 急務 高年齢の労働者 けが増加
- 2025/12/12
- 【地域経済】愛知の中小 賞与35万2422円 冬季調査 前年比7690円減
- 2025/12/02
- 【愛知】お仕事チャレンジ 軌道に 「短時間 支援員同行 報酬」で自信
- 2025/11/19
- 【社会】カスハラ 来秋から対策義務 事例を明記、対応指針も
- 2025/10/10
- 【くらし】副業に訪問介護ヘルパー 「少しずつ仕事をシェア」
- 2025/10/01
- 【愛知】カスハラから労働者守る 県が事業者向けマニュアル
- 2025/09/25
- 【愛知】きんこう経済/春日井・小牧両商議所 地元中小の新卒採用支援
- 2025/09/11
- 【愛知】ひきこもりや高齢者ら 前向けるよう
- 2025/09/09
- 【愛知】突発的に看護師が足りない!どうする?