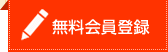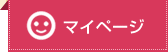転職・求人情報-名古屋市、愛知県、岐阜県、三重県の転職・求人サイト
- 中日しごと情報HOME>
- 就職・転職ニュース>
- 【暮らし】<なくそう長時間労働> ゼロのつく日はノー部活動デーに
【暮らし】<なくそう長時間労働> ゼロのつく日はノー部活動デーに
2017/01/23
長時間労働は、教育界でも問題になっている。特に教員の残業や過労原因として指摘されているのが部活動だ。政府が「働き方改革」に取り組む中、文部科学省は今月、教員の負担減を目的に全国の教育委員会に部活動の休養日を適切に設けるよう通知。専門家も一斉に部活を休む「ノー部活動デー」の推進を提唱する。
「部活が雨で休みになればいいと、心の中で雨乞いをしたことがある」。神奈川県内の公立中学校でサッカー部顧問を務める20代の男性教諭は打ち明ける。
教諭はサッカー経験がないが、昨年4月、前任者の異動に伴い校長に指名されて顧問になった。平日は週5日練習。週末も大会や顧問が集まる役員会、審判講習会などが入って月に3、4日しか休めない時もある。夏休み中も毎日練習があり、8月末には過労が募り朝起きた時に動悸(どうき)がして大量の冷や汗が出るようになった。ちょうど台風が来て雨が降り、やっと練習を休みにできた。
「子どもや保護者の期待があり、顧問の自分からは練習を休みたいとは言えない。『長く練習をすることが美徳』という空気が職員室にも流れていて、部活が長時間労働の温床になっている」と教諭は話す。冬場は午後5時、夏場は午後6時半まで部活を指導。その後に授業準備をし、特に約120人分のテストの採点が重なると帰宅が午後10時を過ぎてしまう。
そもそも部活は教育課程外の活動で、教師に顧問を務める義務はない。だが実際にはほとんどの教師が半ば強制的に部活顧問を担わされているのが実情だ。「学校内には、教師は熱心に部活指導をするべきだという『同調圧力』がある。保護者や世間も、長い時間部活指導する教師ほど『子どもに尽くすいい先生』だと評価しがち」。私立中学での教員経験がある学習院大(東京都豊島区)教育学科の長沼豊教授は言う。
長沼教授は、企業は「残業を減らしても、収益や売り上げが落ちなかった」などの業務改善例を示しやすい一方で、教師は「部活の練習日数を減らしても、大会でいい成績を収めた」などの成果を示しにくいと指摘。教師は部活の活動内容を縮小しにくい環境に置かれていると強調する。
長沼教授は、覚えやすいように毎月ゼロの付く「10」「20」「30」日は部活を休む「ノー部活動デー」にすることを提唱。職員室に貼れるようにと作ったロゴマークを、自身のホームページで印刷できるようにもしている。「一斉に休んで『部活動改革』に取り組み、長時間労働を解消してほしい」と話す。
◆文科省「休養日を」
政府が長時間労働を改善する働き方改革を進める中、文科省も今月6日、中学校の運動部の休養日を適切に設定するよう求める通知を教育委員会に出した。
スポーツ庁は昨年初めて国公私立中学を対象に部活の休養日に関する調査を実施。9534校が回答し、22.4%が1週間のうち固定した休養日を設けていないことが分かった。設けていない学校の割合を都道府県別に見ると東京が63.8%、神奈川45.4%、三重39.1%、愛知20.4%、福井0%と地域差が大きい。
こうした中で三重県桑名市教育委員会は昨年11月、中学校を対象にした独自の部活動ガイドラインを策定。運動部だけでなく文化部も対象で、休養日を週2日設け、少なくとも土日のいずれか1日を休みにすることが望ましいとしている。
(細川暁子)

- 教員の長時間労働解消のために「ノー部活動デー」を提唱している学習院大の長沼豊教授=東京都豊島区で
転職・求人情報検索(名古屋市・愛知県・岐阜県・三重県)はトップから
- 2025/09/11
- 【愛知】ひきこもりや高齢者ら 前向けるよう
- 2025/09/09
- 【愛知】突発的に看護師が足りない!どうする?
- 2025/08/29
- 【社会】夫婦の働き方 十組十色 広がる「ファミリーキャリア」
- 2025/08/27
- 【くらし】地方回帰 移住は今/転職で「生活の質 向上」異動打診機に決意
- 2025/08/22
- 【経済】県内最低賃金1140円に63円引き上げ、審議会答申
- 2025/08/14
- 【社会】保育施設8割 人材不足 政府が初の全国調査
- 2025/08/13
- 【社会】働きながら介護や育児 10年後には・・・ 6人に1人
- 2025/07/18
- 【三重】ビジネスプラン作り 基本から 「グランプリ」向け 相可高生学ぶ
- 2025/07/08
- 【地域経済】子育て・介護しやすく 「短時間正社員制度」を導入
- 2025/06/20
- 【愛知】終業と始業の間 しっかり休息を