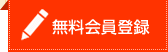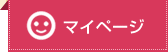転職・求人情報-名古屋市、愛知県、岐阜県、三重県の転職・求人サイト
- 中日しごと情報HOME>
- 就職・転職ニュース>
- 【教育】がんの知識正しく知って 小中高校で授業 医師や患者の体験聞く
【教育】がんの知識正しく知って 小中高校で授業 医師や患者の体験聞く
2016/11/28
がんに対する正しい知識を学ぶ「がん教育」が、各地の学校で始まっている。検診への理解が進むことや、がん患者やがん治療に偏見を持たないようにすることなどが期待されている。 (佐橋大)
◇ ◇ ◇
三重県亀山市の亀山中学校では10月、保健体育の一環で3年生が、がんを学んだ。大腸がんの手術もする外科医で、三重大大学院医学系研究科講師の井上靖浩さんが、がんで亡くなる人が年々増えていることや、喫煙などの生活習慣によってがんになる可能性が高まることを伝えた。「ならないようにと思っていても、なってしまうのががん。早期発見が大事。早く見つければ、治る確率も高まる」と、検診の必要性を訴えた。
続いて、上咽頭がん経験者で法務省津保護観察所社会復帰調整官の荒木求州(もとくに)さん(39)が「20歳でがんになった。そのとき、親に言えなかった。知識がなく、がんになったら死ぬと思っていたから」と語った。「がんに関して自分の思いを言葉にするのには勇気が要る。皆さんは話しやすい雰囲気をつくって」と呼び掛けた。生徒たちは「いい生活習慣を心掛けたい」などと感想を述べていた。
長野県佐久市の佐久平総合技術高校でも、1年生に授業があった。内容は、がんの現状や予防について。池田みすゞ養護教諭が、身近な人にがん検診を勧めるとしたら、どうするかと生徒たちに課題を与えた。生徒たちは、父親や祖母らを想定し、考えた。
厚生労働省によると、がんは1981年から死因の第1位。生涯で2人に1人がかかり、昨年は37万131人が亡くなっている。一方、がん検診の受診率は欧米諸国に比べ低い。
がん教育の推進は、国が2012年度に定めた「がん対策推進基本計画」に盛り込まれている。現在、小学校高学年、中学3年、高校の保健で、生活習慣病の一つとしてがんを扱っているが、同計画は「理解を深めるには不十分」と指摘した。文部科学省は、学校でのがん教育を17年度以降、全国で実施する目標を立て、それに先立ち、14年度からモデル事業を開始。16年度は24道府県の137の小中学校・高校で実施し、講師料などを負担して、授業の内容や効果を研究している。
同省健康教育・食育課の鶴原寛之係長は「検診受診率の向上や、がんになりやすい生活習慣の改善、患者への誤ったイメージの払拭(ふっしょく)につながれば」と話す。
三重、長野両県の授業は、いずれもモデル事業だ。三重県では昨年六校で実施。授業の前後で、がん検診を受診年齢になったら受けようと考える児童・生徒の割合が64%から85%に上昇。「がんになっている人も過ごしやすい世の中にしたい」と考える割合も62%か87%に上がった。
長野県の授業は、文科省が今年4月に作った補助教材を使った。内容が専門的になりすぎず、科学的な根拠を持った標準的な中身になるよう工夫されている。モデル校の一部で使ってもらいながら改善する。
転職・求人情報検索(名古屋市・愛知県・岐阜県・三重県)はトップから
- 2025/12/02
- 【愛知】お仕事チャレンジ 軌道に 「短時間 支援員同行 報酬」で自信
- 2025/11/19
- 【社会】カスハラ 来秋から対策義務 事例を明記、対応指針も
- 2025/10/10
- 【くらし】副業に訪問介護ヘルパー 「少しずつ仕事をシェア」
- 2025/10/01
- 【愛知】カスハラから労働者守る 県が事業者向けマニュアル
- 2025/09/25
- 【愛知】きんこう経済/春日井・小牧両商議所 地元中小の新卒採用支援
- 2025/09/11
- 【愛知】ひきこもりや高齢者ら 前向けるよう
- 2025/09/09
- 【愛知】突発的に看護師が足りない!どうする?
- 2025/08/29
- 【社会】夫婦の働き方 十組十色 広がる「ファミリーキャリア」
- 2025/08/27
- 【くらし】地方回帰 移住は今/転職で「生活の質 向上」異動打診機に決意
- 2025/08/22
- 【経済】県内最低賃金1140円に63円引き上げ、審議会答申