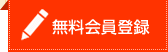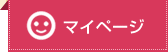転職・求人情報-名古屋市、愛知県、岐阜県、三重県の転職・求人サイト
- 中日しごと情報HOME>
- 就職・転職ニュース>
- 【カルチャー】納得のゆく仕事?「つて」を編み直す人たち
【カルチャー】納得のゆく仕事?「つて」を編み直す人たち
2016/09/07
哲学者・京都市立芸術大学長/鷲田 清一
現在の労働状況を考えるときに、だれもがすぐに思い浮かべるのは〈格差社会〉であろう。増大しつづける「非正規」という就労形態は、低賃金でそれだけでは生計が成り立たない、不安定で先の見通しが立たない、何かの目標に向かって協働しているという実感がもてない、1人ひとりが孤立し交友が広がらない、自身の能力を仕事のなかで鍛えるというチャンスがない…など、それこそ「納得」のゆかないことばかりである。
他方でしかし、正規の職にあるからといって「納得」のゆく働き方ができているわけでもない。先日手にした「We Work HERE」(ミライインスティチュート出版)という本にこんな述懐が記されていた。
◇ ◇ ◇
〈当たり前に就職活動をして、自己分析と自己アピールを繰り返してようやく会社に入って、上から振ってきた仕事を日々こなしながら、役職アップと給料アップを目指す。二重人格的にワークとライフを切り分けて、仕事で溜(た)まったストレスを移動中のスマホゲームやアフターファイブの飲み屋で解消し、週末はテレビで紹介されていた流行(はや)りのお店で買い物をし、食べログ高得点のレストランでおいしい料理を食べ、プライベートライフを満喫することで明日から始まる仕事に備える。〉
「だましだまし」でかろうじて続けられるそんなワークの疲れを、ライフのほうをおもいっきりプライベートに閉じることでわずかなりとも癒やす。しかしこれもまたライフの「だまし」になっていないか…。ワークとライフの足場がともにおぼつかなくなっているのだ。そんななかで「わたしはここにいる」といえる仕事と生活の足場、つまりはそれぞれのHEREを、この本は百人に質問している。ほとんどが企業という大きなシステムにぶら下がって働くことを辞め、「小商い」と「複業」を始めた人たちだ。
作業それじたいが楽しいこと。この作業がじぶん以外の誰かの役に立っているということ。この2つが感じられない仕事は辛(つら)い。それを回避するために、この人たちが企業というシステムに代えたものは何だったのか。
いまどきの言葉でいえば、手作りのネットワーク、かつての言葉でいえば「つて」ではないかとおもう。仕事とは、生きるため、生き延びるためのネットワークをつくることだ。困ったときに「あの人に相談してみよう」といえるような人びとのつながり。「こね」(コネクション)というよりも、頼りにできる手蔓(てづる)、つまりは「つて」である。
もとはといえば、会社とは、1人でやる仕事のリスクを減らし、1人でやるのは困難なチャレンジを可能にするために編みだされた協働のかたちである。個人がもっと活動の枠を拡(ひろ)げられるよう工夫された装置である。それが内に閉じた巨大組織になって、それぞれが組織のシェア(占有率)を競うようになった。本来のシェア(分有)が転倒してしまっているのだ。
◇ ◇ ◇
若い人たちの「小商い」と「複業」というふるまいには、やむなくそうせざるをえなかった面もあるにせよ、「働く」ことの意味への、身を挺(てい)した問いが含まれている。素手で「つて」を編んでゆくさまざまの(愉(たの)しい?)知恵もある。「キャリア教育」や「キャリアデザイン」の講座を受けるよりも、じぶんにとって仕事における「納得」とは何かを考えるほうが、じぶんの可能性を広げるには先なのではないかとおもう。
転職・求人情報検索(名古屋市・愛知県・岐阜県・三重県)はトップから
- 2025/12/12
- 【地域経済】愛知の中小 賞与35万2422円 冬季調査 前年比7690円減
- 2025/12/02
- 【愛知】お仕事チャレンジ 軌道に 「短時間 支援員同行 報酬」で自信
- 2025/11/19
- 【社会】カスハラ 来秋から対策義務 事例を明記、対応指針も
- 2025/10/10
- 【くらし】副業に訪問介護ヘルパー 「少しずつ仕事をシェア」
- 2025/10/01
- 【愛知】カスハラから労働者守る 県が事業者向けマニュアル
- 2025/09/25
- 【愛知】きんこう経済/春日井・小牧両商議所 地元中小の新卒採用支援
- 2025/09/11
- 【愛知】ひきこもりや高齢者ら 前向けるよう
- 2025/09/09
- 【愛知】突発的に看護師が足りない!どうする?
- 2025/08/29
- 【社会】夫婦の働き方 十組十色 広がる「ファミリーキャリア」
- 2025/08/27
- 【くらし】地方回帰 移住は今/転職で「生活の質 向上」異動打診機に決意