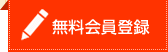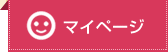転職・求人情報-名古屋市、愛知県、岐阜県、三重県の転職・求人サイト
- 中日しごと情報HOME>
- 就職・転職ニュース>
- 【暮らし】進まない有休消化 バカンス遠い日本
【暮らし】進まない有休消化 バカンス遠い日本
2016/07/25
◆夏休み何日取れる?
夏休みシーズンに入り、お盆を中心に休暇の予定を練っている家族も多いだろう。だが、日本では長期の休みは取りにくく、年次有給休暇(有休)さえ消化できていないのが現状だ。有休の法的位置付けと、取得に向けたポイントを専門家に聞いた。
東京都世田谷区の女性会社員(47)は、毎年夏に2週間の休暇を取ってイタリア旅行を楽しんでいる。休む期間は年明けには決め、それに向けて同僚と仕事の段取りを調整する。「休みを取るという目標があると、仕事のモチベーションも上がる」と話す。
とはいえ、女性のように長期の休暇を楽しめるのは日本ではまだ少数派だ。厚生労働省の調査によると、2015年の有休取得率は47・6%。従業員数千人以上の大企業でこそ52・2%と半分を超えているが、百人未満だと取得率は四割少々。有休さえ消化できないのでは、欧米のように長期のバカンスを楽しむのはほど遠い。
労働問題に詳しい名古屋北法律事務所(名古屋市北区)の白川秀之弁護士(37)は「欧米では労働時間規制が厳しいので長期の休みを取りやすいが、日本には長期休暇を保障する法律はない」と指摘する。
その中で、有休は労働者の権利として法律で定められている。労働基準法39条には、6カ月以上働き続け、勤務すべき日数の八割以上出勤していれば、10日間の有休を与えなくてはならないと定めている。長く働き続ければ有休も増える。正社員だけでなく、雇用形態にかかわらず非正規やパート従業員にも認められている。
「わが社に有休の制度はないと主張する企業があるが、これは使用者が絶対に与えなくてはならない義務だ」と白川弁護士は強調する。
義務というからには罰則もある。労働者の求めを拒否して有休を与えなかった場合、使用者には六カ月以下の懲役または30万円以下の罰金が科せられる。「違反すれば犯罪ということになる」と手厳しい。
企業側には、休むタイミングを労働者にずらしてもらう「時季変更権」が認められている。しかし同法では、「有休を与えることで、事業の正常な運営を妨げる場合」という制約を付ける。「単なる業務繁忙や人員不足程度では認められません。また、企業側がその事情を説明できなければならない」と解説する。
◆なぜ? 「職場に迷惑かけられぬ」まず権利意識を
有休の取得率が上がらないのはなぜか。
「権利を行使しないからです。日本では職場に迷惑をかけてはならないという意識がなお強い。企業に対して働く側の立場が弱いという現実もある」。白川弁護士は言う。
休める職場づくりの鍵は労使交渉にあるという。欧米は産業別の労働組合が多く、いろんな企業をまたいで労働者が企業と交渉し、例えばバカンスの休みは何日にするといった協約を結ぶ場合が多い。労働者が使用者側とどう休むのか、業務の必要性も加味して話し合うのがベストという。
日本の現実は労組の組織率が2割を切り、企業との交渉力も落ちる一方。非正規労働者はその企業に長くいる人が少なく、きちんと使用者と交渉する力は弱い。
「有休は法律で認められた権利という意識を持つことが大事。与えてもらっているという感覚では、せっかくの権利も行使をためらってしまう。まずは気軽に有休を取得し、広めていくのが大切だ」と話している。
(三浦耕喜)
転職・求人情報検索(名古屋市・愛知県・岐阜県・三重県)はトップから
- 2025/12/02
- 【愛知】お仕事チャレンジ 軌道に 「短時間 支援員同行 報酬」で自信
- 2025/11/19
- 【社会】カスハラ 来秋から対策義務 事例を明記、対応指針も
- 2025/10/10
- 【くらし】副業に訪問介護ヘルパー 「少しずつ仕事をシェア」
- 2025/10/01
- 【愛知】カスハラから労働者守る 県が事業者向けマニュアル
- 2025/09/25
- 【愛知】きんこう経済/春日井・小牧両商議所 地元中小の新卒採用支援
- 2025/09/11
- 【愛知】ひきこもりや高齢者ら 前向けるよう
- 2025/09/09
- 【愛知】突発的に看護師が足りない!どうする?
- 2025/08/29
- 【社会】夫婦の働き方 十組十色 広がる「ファミリーキャリア」
- 2025/08/27
- 【くらし】地方回帰 移住は今/転職で「生活の質 向上」異動打診機に決意
- 2025/08/22
- 【経済】県内最低賃金1140円に63円引き上げ、審議会答申