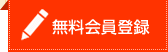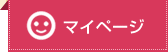転職・求人情報-名古屋市、愛知県、岐阜県、三重県の転職・求人サイト
- 中日しごと情報HOME>
- 就職・転職ニュース>
- やってみました 記者たちの職業体験ルポ かじ屋
やってみました 記者たちの職業体験ルポ かじ屋
2010/05/26
熟練の技で包丁長持ち
右手の金づちを振り下ろしてオレンジ色に光る鉄を打つと、顔の近くにまで火の粉が飛ぶ。怖い-。思わず体をのけぞらせてしまう。金づちの重たさにしびれてきた腕をよろよろと振り上げる様子に、「明日は筋肉痛だね」と傘寿を迎えた熟練工に笑われ、貧弱なわが身を恥じた。
設楽町八橋の自宅敷地内の工房でかじ屋を営む、安藤義久さん(80)。ステンレス製の包丁すらほとんど握らない単身赴任の記者には無謀と自覚しつつ、昔ながらの技法で刃物を作り出す仕事を紙面で紹介したいと工房に入らせてもらった。
赤々と光る炭の中に差した鉄の延べ棒を金ばさみで抜き取り、鋼の台に乗せる。「刃ではなくみねの方を打って」とのアドバイスを受け、金づちを振る。しかし打った跡がうろこのように汚く残ってしまうし、鉄は伸びてくれない。
「もうあかん」の合図で再び延べ棒を炭の中に入れ、数十秒後に抜き取り、打つ。この作業を繰り返す。
炭の暑さと腕のしびれで早くもギブアップ気味の記者に「もうやめるの?」と問われ、「まだまだ」と意地を張った。
町内の職人のもとで修業した安藤さんが同所に工房を構えたのは六十年ほど前。当時は町内に十軒以上のかじ屋があったが、今は一軒のみ。
その安藤さんも、現在は注文を受けていない。国の計画する設楽ダムの水没地に自宅が含まれるため移転せざるを得ず、転居までに製造できるのは既に受けた五百件で限界と判断したためだ。
記者とバトンタッチしたところで「カン、カン、カン」と小気味よい金属音を響かせ徐々に伸ばしていく安藤さん。余計な部分を切り落とすなどし、二時間前までただの延べ棒だったのが文化包丁の形に仕上がった。この後、研磨などを経て一日で完成する。
「かじ屋なんてもうからん」と話す一方、「うちの包丁は一生使っても使い切れないよ」と語る表情は、職人としての経験や自信にあふれているように感じた。(諏訪慧)
【メモ】職人に師事して修業が必要で、安藤さんは8年を経て独立。収入は販売数と価格設定による。安藤さんの場合、注文は6000円の文化包丁がほとんどで、毎日つくっても「年金と合わせて暮らすのがやっと」。技術料を高く設定し1万5000円で売る出刃包丁やなたが売れれば収入は増えるが、「昔は需要あったが、今はあかん」とのこと。

- 鉄の延べ棒を伸ばし文化包丁に仕上げていく安藤さん=設楽町八橋で
転職・求人情報検索(名古屋市・愛知県・岐阜県・三重県)はトップから
- 2025/09/11
- 【愛知】ひきこもりや高齢者ら 前向けるよう
- 2025/09/09
- 【愛知】突発的に看護師が足りない!どうする?
- 2025/08/29
- 【社会】夫婦の働き方 十組十色 広がる「ファミリーキャリア」
- 2025/08/27
- 【くらし】地方回帰 移住は今/転職で「生活の質 向上」異動打診機に決意
- 2025/08/22
- 【経済】県内最低賃金1140円に63円引き上げ、審議会答申
- 2025/08/14
- 【社会】保育施設8割 人材不足 政府が初の全国調査
- 2025/08/13
- 【社会】働きながら介護や育児 10年後には・・・ 6人に1人
- 2025/07/18
- 【三重】ビジネスプラン作り 基本から 「グランプリ」向け 相可高生学ぶ
- 2025/07/08
- 【地域経済】子育て・介護しやすく 「短時間正社員制度」を導入
- 2025/06/20
- 【愛知】終業と始業の間 しっかり休息を