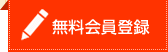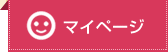転職・求人情報-名古屋市、愛知県、岐阜県、三重県の転職・求人サイト
- 中日しごと情報HOME>
- 就職・転職ニュース>
- 【暮らし】残業減へ 社内で効率化
【暮らし】残業減へ 社内で効率化
2010/04/22
「今週中にグループ各社を回りたい」
「予定に空きがあるから手伝うよ」
総合事務機器メーカー「コクヨ」(本社大阪市)の東京品川オフィス。人材開発部の社員四人が、一週間の予定を報告し合う。
週に一度のこの会合は残業削減の狙いもある。業務量の多い社員がいれば、別の社員がシェアする。呼び掛け人の小林靖課長(51)は「メンバーの業務量を平準化して時短を目指す」と話す。
仕事にメリハリをつけて効率化を図ろうと、同社は二〇〇八年六月から「働き方見直しプロジェクト」運動を始めた。部ごとに半年間行い、二百人以上が取り組んだ。
中身は、業務の可視化だ。部員は出社したら、基本的に残業をしない前提で、十五分刻みの業務予定を優先順位をつけてメールで報告し、終業時にも結果を送る。これらの情報を部全体で共有。朝と夜の“ズレ”を分析、業務改善に生かすというサイクルを続け、生産性を上げる。冒頭の会議のように、運動の考え方が浸透した取り組みも出てきた。
残業は悪役扱いだ。運動推進役でダイバーシティー推進リーダーの赤木由紀さん(39)は「多様化するニーズに対応できる付加価値の高い商品を生み出すには、自分の時間を持つことが必要。情報やアイデアをインプットする時間がないと成果が平板になる」と語る。長時間を前提にすると、人件費の負担に加え、育児や介護に直面する社員の活用も阻害しかねない。
不景気なので運動は業績には直接結びつかなかったが、労働時間の短縮は成功。オフィス家具の営業部門は総労働時間を半年で27%削減、業務効率も高まった。今後、グループ全体に広げる考えだ。
同社のように生産性を高めて残業を減らす会社は増えてきた。しかし、日本の労働生産性は低い。日本生産性本部が実施した〇八年国際比較で、日本はOECD三十カ国中二十位、G7で最下位だ。
人事コンサルタント業「ワーク・ライフバランス」の小室淑恵社長(35)は「売上高など上積み方式の評価だと、残業して成果を上げようとする。限られた時間で高い付加価値の商品を作らないと世界で勝てない」と説く。
◆休息を義務に 制度導入の動き
労働時間の上限を規制して、働き過ぎを防ぐ取り組みもある。
労働基準法では労働時間を定めているが、同法第三十六条に基づいた「特別条項付き三六(さぶろく)協定」を結べば、条件付きで社員を何時間でも働かせられる。例えばソフト開発なども業務の特性上、長時間労働を強いられることがある分野だ。
情報通信建設、情報サービス業など二百三十七労働組合(単組)でつくる「情報労連」傘下の一部組合は昨年の春闘で、終業時間から次の始業時間までの間に、連続した休息時間の付与を義務付ける「勤務間インターバル制度」を導入、使用者と合意した。情報労連の縄倉繁・政策局長(47)は「労働者の健康と生活を脅かす長時間労働に歯止めをかけたかった」と話す。
同制度により、労働時間に“天井”ができる。週六日働き、最低十時間の勤務間の休息が計五回あるとすると、週労働時間は最大でも九十四時間(24時間×6-10時間×5)に抑えられる。残業が長引き、始業時間まで休息が足りない場合には、不足分が翌日の労働時間から免除され、有給扱いとなる仕組みだ=図。
ただ、今春闘までに締結したのは、まだ十五単組にすぎない。休息時間も、情報労連が参考にしたEUが十一時間なのに対し、長くて十時間、短いとわずか七時間だ。縄倉局長は「企業の理解も得て少しずつ拡大したい」と話している。
転職・求人情報検索(名古屋市・愛知県・岐阜県・三重県)はトップから
- 2025/09/11
- 【愛知】ひきこもりや高齢者ら 前向けるよう
- 2025/09/09
- 【愛知】突発的に看護師が足りない!どうする?
- 2025/08/29
- 【社会】夫婦の働き方 十組十色 広がる「ファミリーキャリア」
- 2025/08/27
- 【くらし】地方回帰 移住は今/転職で「生活の質 向上」異動打診機に決意
- 2025/08/22
- 【経済】県内最低賃金1140円に63円引き上げ、審議会答申
- 2025/08/14
- 【社会】保育施設8割 人材不足 政府が初の全国調査
- 2025/08/13
- 【社会】働きながら介護や育児 10年後には・・・ 6人に1人
- 2025/07/18
- 【三重】ビジネスプラン作り 基本から 「グランプリ」向け 相可高生学ぶ
- 2025/07/08
- 【地域経済】子育て・介護しやすく 「短時間正社員制度」を導入
- 2025/06/20
- 【愛知】終業と始業の間 しっかり休息を