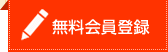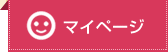転職・求人情報-名古屋市、愛知県、岐阜県、三重県の転職・求人サイト
- 中日しごと情報HOME>
- 就職・転職ニュース>
- 【流儀あり】「死に慣れるな」繰り返す ティア・冨安徳久社長
【流儀あり】「死に慣れるな」繰り返す ティア・冨安徳久社長
2010/02/11
価格破壊とよく言われますが、秘訣(ひけつ)なんかないんです。これまでが適正な料金でなかっただけ。
(独立前に)葬儀会社に勤めていたころ、異業種交流会に参加して名刺交換をしたら、目の前で名刺を破られた。「いくら異業種といっても葬儀屋はねえ」って。悔しかったですね。
でも、社内で責任ある立場になって(葬儀用品の)原価を知った時、業界にも問題があるって分かったんです。何でこんなに暴利を得ているんだと。利益率が30%とか40%とかある。そのころ(約20年前)の名古屋市内の葬儀料金の平均単価は300万円。その半額でやっても8~10%の利益率が出せるって思いました。
葬儀社が決めた、勝手な価格だったんです。嫌がる仕事をやっているからもうけて当然という考え方が業界に蔓延(まんえん)していました。消費者は葬儀をタブー視し、業界はブラックボックス化する。先輩にこう指導されましたよ。「相手の家を見て、車を見て、役職を聞いてから葬儀料金を言え」って。
自分のやっていることは世のためになるはずなのに、そうなっていない。公憤が原点にあるんですよ。それで、適正料金を発信できる会社をつくろうと思いました。
経営で一番大切にしてきたのは人です。“人が差別化になる業種”と思ってきました。それがなされていない業界だったから。
サービスの限界は、その人の感性で決まります。感性の教育で大事なのは「繰り返し」。現場に放り込んだら忙しさに追われてだんだん“作業”になる。遺族の悲しみに寄り添うことを忘れてしまうんです。「『死』に慣れるな」と繰り返し説いています。
葬式は1回1回、すべて違う。打ち合わせの数時間で、亡くなった方の人生を遺族から聞き出すんですね。庭先でアジサイをよく眺めていたと聞いたら、アジサイの写真を撮って入り口に飾る。それをサプライズでやるんですよ。
思いもよらないことをやらないと感動って生まれないんです。マニュアルではできないですよ、相手の気持ちをくみ取る感性がないと。意識してやるのでは駄目。無意識に、自然に行動できないと。だからこそ「繰り返し」なんです。
【とみやす・のりひさ】 79年、愛知県立豊丘高校卒。18歳で山口県の葬儀社に就職。その後、東海地方の大手葬儀互助会などの勤務を経て97年にティアを設立。06年、名証セントレックスに上場(現在は名証2部)。08年に「ぼくが葬儀屋さんになった理由」を出版、注目を集める。現在は愛知、岐阜、大阪、和歌山の4府県に37会館(フランチャイズを含む)を運営。愛知県一宮町(現豊川市)出身。49歳。

- ティア社長の冨安徳久氏=名古屋市北区のティア本社で
転職・求人情報検索(名古屋市・愛知県・岐阜県・三重県)はトップから
- 2025/09/11
- 【愛知】ひきこもりや高齢者ら 前向けるよう
- 2025/09/09
- 【愛知】突発的に看護師が足りない!どうする?
- 2025/08/29
- 【社会】夫婦の働き方 十組十色 広がる「ファミリーキャリア」
- 2025/08/27
- 【くらし】地方回帰 移住は今/転職で「生活の質 向上」異動打診機に決意
- 2025/08/22
- 【経済】県内最低賃金1140円に63円引き上げ、審議会答申
- 2025/08/14
- 【社会】保育施設8割 人材不足 政府が初の全国調査
- 2025/08/13
- 【社会】働きながら介護や育児 10年後には・・・ 6人に1人
- 2025/07/18
- 【三重】ビジネスプラン作り 基本から 「グランプリ」向け 相可高生学ぶ
- 2025/07/08
- 【地域経済】子育て・介護しやすく 「短時間正社員制度」を導入
- 2025/06/20
- 【愛知】終業と始業の間 しっかり休息を